こんにちは紫乃です。
今回は泡沫のユークロニアに登場する作中単語の考察をしていきたいと思います。
以前スタッフコラムにて、実際に存在する日本語の単語を多く使用しているとのお話がありました。
その為作中で使用される名詞に着目して意味を調べてみました。
後半のほうが考察色強めになっていますので、最後までお読み頂けますと嬉しいです。
【2025年9月追記】
FDを進めたことで考察が進み、各所修正・追記した部分が多くあります。
作中単語考察
人名について
古典等で使用された古語から季語まで、花鳥風月、日本古来の単語が多い印象です。
辞書みたいにどんどん並べていきます。
人物と単語の意味で特に関連性がなさそうなものもありますが、日本語の奥深さを感じられました。
矢代
「やだい」と読ませたり様々な意味がありました。
個人的には「やがわり」と読ませる意味が印象的です。
『他人の身代わりとなって矢に射当てられること』
銀湾の間者という危険な役目を負わされた彼が連想されました。
帷
「夜の帳」の帳と同じように覆い隠すものの意味。
戦の作戦を練る場所・大将の陣営を意味する「帷幄」(いあく)や「帷幕」(いばく)に使われている漢字であり、男らしさや勇ましさを表現したい場合に適するそうでした。
花街の顔役・不知火の首領であり男気がある帷らしいです。
淡雪
うっすらと積もったやわらかで消えやすい雪。
春の季語。
依
「頼る」といった意味、「依然」という単語がある通り「そのまま」の意味もあります。
露草と雛菊は彼らのイメージフラワーでもあるように花の名前です。
花言葉はこちらの記事で紹介しています。
続く柊・石蕗も植物の名前です。
柊
節分で魔除けとして飾られる棘のある葉の植物。
花言葉には「先見の明」などがあります。
石蕗
「謙譲」「謙遜」「困難に負けない」といった花言葉を持つ食べられる植物。
妾の子としての出自を持つ彼っぽい意味を持っていました。
ここからはサブキャラクターです。
FDの新キャラも含みます。
まずは流れを汲んで植物関連のキャラから。
枸橘
中国原産のミカン科の落葉低木。
枝に棘がある。触ると危険。
実や花が季語となっている。
賢木
神域にある常緑樹の総称。
神事に用いる榊と同様の意味。
上記は神と人を繋ぐもの、依代の意味があります。
大樹と民を繋ぐ存在としての意味が込められているのかもしれません。
夏の季語でもあります。
松柏
漢字の通り松と柏。
節(みさお)を守って変えないことの例えとしての意味も。
葵
花の名前で「高貴」といった花言葉を持っています。
月や天候に関する単語も多く使用されています。
露草の半月堂もそうですね。
雨月
旧暦5月の異称。
名月が雨で見られないことも意味する秋の季語です。
朧
ぼんやりとかすんでいるさま。
春の季語。
「朧月夜」のように月と使用されることも多いです。
朔
いくつか意味がありましたが、新月を表すのがイメージに近いです。
佳月
旧暦3月の異称。
名月を意味する春の季語です。
鳴神
雷や雷鳴を指すという説があります。
氷雨
夏の季語として雹(ひょう)や霰(あられ)の意味。
冬の季語として冷たい雨やみぞれの意味。
最後にその他の部類の単語のキャラクターです。
藍白
日本の伝統色。藍染の中でも最も淡い色で黄みを含んだ淡い水色。
千鳥
小鳥の種類の総称でもありますが、日本の伝統的な文様である千鳥文様から来ているように思います。
周防
現在の山口県東部の旧国名。
ちなみに左丞相の常陸は茨城県北東部の旧国名です。
右丞相の周防が西(左)の国名で左丞相の常陸が東(右)の国名なのは不思議に思うでしょう。
日本では古来左の方が上座であるという考え方があり、雛人形で言うと男雛から見て左が左大臣、右が右大臣になっています。
つまり向かって右が左大臣、左が右大臣になるんです。
この考え方を当てはめると周防と常陸の名付けにも納得がいきます。
実際常陸は年齢も高く、関白の地位でもあったということで上位の立場です。
潮路やすず音はそのままの意味ですかね。
さて全員分人名を紹介した所で、名付けのざっくりとした法則を見つけました。
植物 →凍玻璃の貴族関連
月関連 →敵役
天候 →禁域関連
まず1つ目、植物関連の名前は一番数が多いです。
藍白は色の名前ですが、藍という植物が存在します。
松柏も今は泉下の住人ですが、凍玻璃の貴族出身です。
植物は凍玻璃では希少な為、身分として割合の少ない貴族のイメージと合わせたのではと推測しています。
(依だけが植物から名前を取っていないので、ここでも彼の異質さが感じられます)
続いて月に関する名前を持つ雨月・朧・朔・佳月は全員主人公と対する立場だったことがある類似点があります。
夜という暗い場所で輝く存在という意味合いを含んでいるのかもしれません。
最後は禁域関連の人々です。
過去近侍であった淡雪、現近侍である雨月・氷雨、また鳴神も当てはまります。
大樹という凍玻璃では神に近い存在の威光を受けていることから、神が操っているかのような天候の名が与えられたのではと考えています。
名称について
ここからは場所や機関などの名称について考察していきます。
凍玻璃
寒さで凍てついたガラス。冬の季語。
冬のガラスは寒暖差にさらされるイメージがあります。
中はぬくぬく暖かいが実際は厳しい寒さということから、理想郷の真実を表しているのかもしれません。
東瀛
東の方の海。日本の異称として用いられることも。
扶桑と関連性あり。
銀湾
天の川の別称。秋の季語。
禁域
侵入してはいけない領域。
扶桑
古代中国で太陽の出る東海の中にあるといわれた神木。
ここから日本の異称の意味も。
ユークロ内では禁域に植わっています。
泉下
死後の世界。あの世。
鴉芙蓉
芙蓉は花の名前で「心変わり」という花言葉を持ちます。
墨染の香の黒と正気を失わせる薬物ということからの命名でしょうか。
不知火
九州の有明海・八代海などで夜間に見られる光の異常屈折現象。
創作でよく使われる言葉ですがこんな意味だったとは。
黒鶴
実際の鶴の種類。
上記の通り、中国の伝承で描かれた日本に関する単語が名称に使用されていました。
さらに深掘っていくと、凍玻璃は日本の江戸時代になぞらえている部分が多くあります。
柳営
将軍のいる所。幕府。
大樹
征夷大将軍の唐名。
大樹は大きな木の他にも中国の名称で将軍の意味があるとは思いもしませんでした。
FDの柊√では、雛菊が大樹の妻のことを「御台所様」と話していたのですが、こちらは将軍の正妻という意味なので大樹と対応する形となります。
因みにゲーム内時点の大樹と柳営の役割は、日本の歴史に当てはめると下記の通りだと思います。
天皇(形式上の最上位):幕府(将軍が実権を握る)
大樹 : 柳営
ただ単語の意味から推測すると、最初は大樹が将軍として政治の実権を握っていた可能性も考えられます。
そもそも凍玻璃が属する国家である東瀛には朝廷が存在し、太政官制に基づき帝を中心に左丞相・右丞相らが政治を取り仕切っていました(銀湾は全体的に平安時代がベースに感じます)。
その中で凍玻璃は自治を認められていたことから、帝とは異なる存在である大樹(将軍)が治める都市という意味があったのかもしれません。
そして徐々に組織である柳営の比重が増し、大樹個人は象徴として天皇化し現在の形になったのでしょうか。
他にも東瀛が鎖国をしていたことや東宮(皇太子)という身分が存在すること、凍玻璃に城下町(作中では城下街)が存在することからも時代性を感じます。
カラクリも実際日本の江戸時代に発展した技術ですし、玻璃病は江戸末期~明治時代に流行した結核が連想されます。
その中で銀湾に訪れた初代大樹は考えてみるとペリーみたいな存在です(開港は求めていませんが)。
その後凍玻璃が異国との交易を開始するのも日本の歴史に近いのではないでしょうか。
また江戸時代には武士・百姓・町人といった身分制度があり、住む場所が区別されていたというのも凍玻璃と同じです。
凍玻璃内では貴族=武士の特権階級に当たります。
外敵から凍玻璃を守る存在であり、血を見ても気分が悪くならないといった他害制御機構を外れた設定にも反映されていました。
貴族の子女が女学校で薙刀の訓練をするという雛菊の話からも武士との関連性が読み取れます。
そして、えた・ひにんといった差別されていた人々が凍玻璃では泉下の住民ということになるでしょう。
最後に、この作品はこれまでのやり方や風潮への疑問がテーマにあったかと思います。
これは江戸時代の終わりである大政奉還などの幕末から明治維新のイメージが重ねられているのではないでしょうか。
凍玻璃が大樹をなくし議会制の民主主義へ進む可能性があることもこの説の根拠になるのではと考えています。
FDのアナザーストーリーでは銀湾への使節団が派遣されますが、こちらからは明治初期に欧米を訪問した岩倉使節団が連想されます。
また雛菊や葵が通っていたとされる女学校も同時期に日本の歴史で開設されていました。
さらに、この日本の江戸末期~明治をベースに西洋の要素を掛け合わせて泡沫のユークロニアという作品が作られていったのではとも感じています。
考えられる要素は下記の通りです。
・錬金術を筆頭に、蒸気機関や外見の特徴、連合国の記述から初代大樹はイギリス人でないかと予想できる。
・銀湾は水の都であるイタリアのベネチアに似ている。
・凍玻璃という存在は旧約聖書のノアの箱舟の逸話に類似している。
ノアの箱舟で起きる洪水は、水害を起こすという意味で狂飆とも似ています。
またプロローグの映像で登場する凍玻璃には舟を漕ぐ櫂のようなものが描かれており、箱舟をイメージした裏付けにもなるのではないでしょうか。
初代大樹を助けた東の民だけが、ノアの箱舟のように狂飆から救われたということかもしれません。
終わりに
今回はひたすら文字での説明がメインな所最後までお読み頂きありがとうございます。
最後の方は日本史の復習みたいになりました。
うろ覚えな部分あり&FD途中なのに急にこの記事を書き始めたので、プレイ後に考察が進む部分があるかもしれません。
最初はふんわり和風の単語が多いなとか和製スチームパンクっぽい世界観だなと思っていたくらいだったので、想像以上に考察が進み調べるのが楽しかったです。
<参考>
コトバンク [ 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 ]
「とばり」の意味とは?「帳」など漢字や熟語も紹介!類語・英語も | TRANS.Biz
https://greensnap.co.jp/columns/holly_language
ツワブキ(石蕗)の花言葉|種類や花の見頃の季節は? | HORTI by GreenSnap
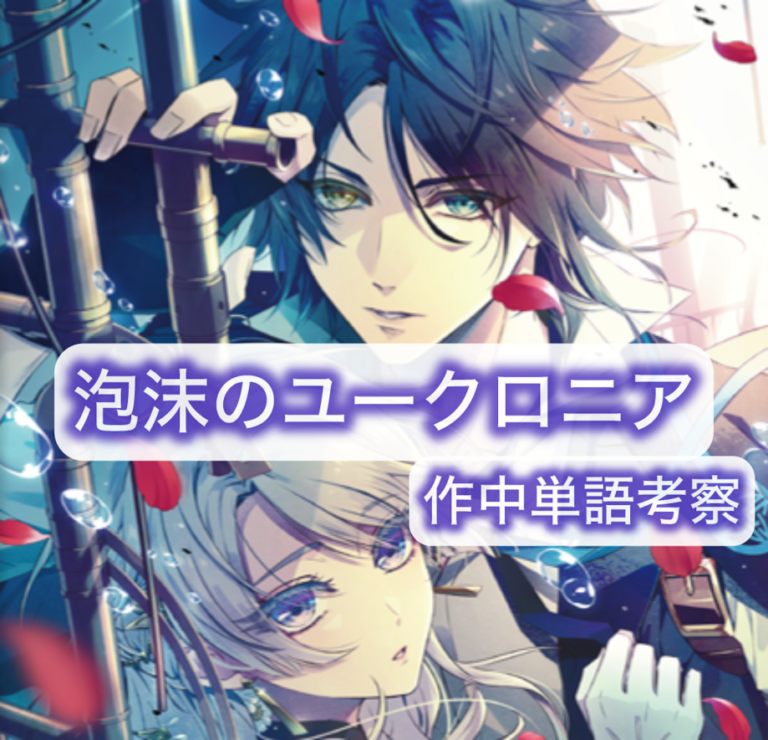

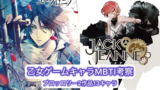


コメント